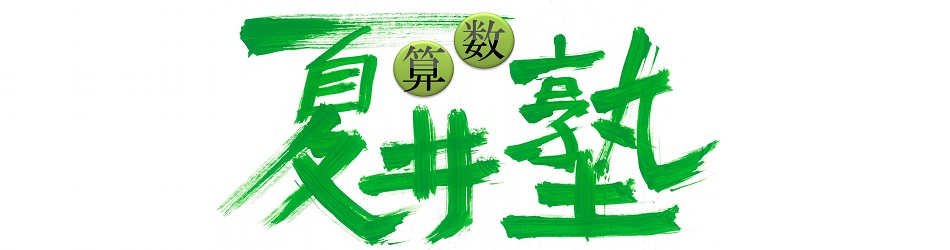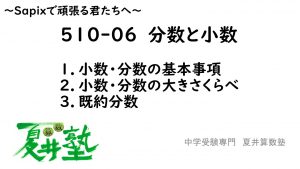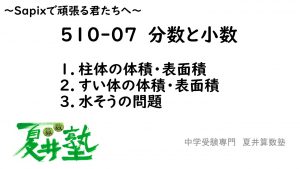中学受験Q&A(3)~模試の活用法と伸び悩みの解消法~
中学受験を行う上で色んな疑問等々が出てくるかと思います。
それについてザクザクと答えていこうというコーナーになっております。
宜しくお願いいたします。
中学受験の時期別の悩み(志望校・模試・過去問・伸び悩みなど)をまとめて整理した全体像は、中学受験算数Q&A|時期別の悩み整理(全体像はこちら)をご覧ください。
公開模試は9月から受けた方がいいですか?
この質問は、おそらく「9月以降、通っている塾以外の模試を受けた方がいいのか?」という内容に近いのではないかと思います。
現在の実力を確認するために、通塾先の公開模試(マンスリー/組分けテストなど)だけでは機会が少ないのでは?と感じ、他塾の模試を追加で受けようと考えるケースはよくあります。
しかし、基本的に強くおすすめはしていません。
理由は、模試ごとに 問題の“個性”や出題傾向が大きく異なる からです。
A塾の模試では頻出の形式が、B塾では全く出ない。その逆もあります。また、A・Bどちらにもない形式がC塾だけに出る、といったケースも珍しくありません。
実際の入試で、過去問を一切解かずに受験会場へ向かう人がいない のと同じで、模試も傾向を知らずに受けると結果が出にくく、不安だけが増えてしまうことが多いのです。もし受けるなら、過去問を数年分見て形式を把握してから にしてください。
さらに、9〜10月以降は志望校の過去問演習が本格的に始まる時期でもあります。
この時期は「より多く模試を受けること」よりも、志望校対策に時間を使った方が成果に直結します。
結論としては――
他塾模試は基本的におすすめしません。
模試より、志望校の過去問に時間を投資した方が合格に近づきます。
公開模試はどこを受けた方がいいですか?という事になります。
これは言い方がちょっと難しい所ではありますが、一番行きたい学校の受験生が多そうな所を受けるというのがまず鉄則になるかと思います。
例えば、もの凄く難易度の高い学校を目指しているのにもの凄い簡単な模擬試験を受けても結果ってよく分からない訳です。
要は、同じ土俵で比べられる生徒さんがそんなに多くないからという事になります。
もちろんどの模試でもこれぐらいの成績があればこれぐらいの学校には合格出来ますよ、といういわゆる合格可能性というものを判定する事は可能ですが、より精度が高いものという事を考えると、やっぱりそれは同条件、同じような、似たような成績をもった生徒さんがたくさん受験しているものという事になるかなと思います。
学校によってはその学校の専用の模擬試験が当然あったりします。
開成オープンみたいなものです。
というものもありますので、そういったものを受験しながらどういった結果が出るか、どれぐらいの問題が解けるか、他の生徒さんは同じような問題をどれぐらい解けているんだろうかという事が分かるという形になるので、そういったものを受験されるのも当然あるかと思います。
ですが、当たり前ですがレベルに合ったものをちゃんと受験するという事は結構徹底して欲しいなと思います。
その意味でも先ほど申し上げた通りで、全然別の所を一回試しに受けてみようというのはあまりお勧めしません。
レベルが違う、そもそも傾向も違うからという所がその回答になるかなと思っています。
伸び悩んでいる子供はどうしたらいい?
生徒さん、中学受験生は何万人もいる訳で、その中でもちろんスンスンと伸びていく生徒さんもいれば、そうじゃない生徒さんもちろんやっぱりいらっしゃいます。
伸びるといっても、目標設定がこの辺だという事になった時に、この辺までちゃんとこれる生徒さんもそんなに多くない訳です。
競争ですからそれは仕方がない部分があるんだという事になります。
これは色んな生徒さんを拝見していて全体的な傾向として感じる所でありますが、伸び悩んでいる生徒さんに共通している事が、基本的に僕、私はこれだけ頑張っているのに全然成績が上がらないという気持ちになってしまっている事が結構多いです。
要は、モチベーションに関わる勢いで出来ないなと思い込んでしまうという所はあるんじゃないかなと思います。
それに対する回答としてはおそらく二つあると思います。
一つ目が、そもそも本当に一生懸命やっているのか?
言い方が難しいですが、相対的に頑張っているのかどうかという所は結構でかいかなと思います。
要は、A君の一生懸命勉強したとB君の一生懸命勉強した、は意外とレベルが違かったりするという事が多かったりします。
例えば、計算テキストがあって、この計算テキスト1ヶ月をやるんだよと決められていても、これを1週で済ます生徒さん、2週で済ます生徒さん、3週頑張ってやる生徒さん、当然やっている内容が違います。
やっている分量も違いますので、出てくる結果も相当違うんですが、計算テストやってる?と聞いたら計算テストはやっていると全員答えます。
その粒度の違いというものの積み重ねが最終的な結果に影響を及ぼす事は結構多いんじゃないかなと思います。
なので、どの程度までやったらいいのかという事はちゃんともう一回見極めて考えてもらった方がいいんじゃないかと思います。
実はもうちょっと頑張れる事があるんじゃないか?と所を考えるという所になります。
あと一方で、考え過ぎてどうしても飲み悩んでしまうという事になります。
これもよく現場というか、授業をしている中でよく遭遇しますが、凄い頑張っているんだけど一切成績が伸びない、停滞していると言われる方が結構いらっしゃいます。
ですが、これは停滞じゃないんです。
全員が進化していく中でそのスピード感が若干違うというだけの話なんです。
ですので、伸び悩んでいる、要は、何も進んでないんだと考えてしまいがちですが、そもそも学習項目1個1個をちゃんと吸収してある程度勉強出来ている状態ではあると思いますので、そのスピード感をどうするか、という事を考えなきゃいけないっていう所になります。
なので、伸び悩んでいる=止まっている訳ではないんだ、という事も強く理解して欲しいなと思います。
進学塾に通わせるべきですか?
難しい質問ですね。
当塾も進学塾では一応あります。
この質問の意図としては、おそらく通常のいわゆる補習塾というんですかね、受験を想定しないような塾に通われている中で、そこからでも受験が出来るのか。
あとは受験しようと思ったタイミングでそこから進学塾に移っていく事が出来るのかどうか、という所になるのかなと思います。
これは結構大変な部分と大変じゃない部分というのはおそらくあると思います。
もちろん中学受験を考えてあげると、算数で言うならば小学校4年生から2年半カリキュラムが組まれているという状態になっています。
なので、これにまずキャッチアップする、追いついていくという必要性はどうしても出てきます。
大体イメージで言いますと、小学校4年生のタイミングで多分1.5年分ぐらい普通の小学校のカリキュラムよりは進んでいる感じになります。
なので、それを考えていくと中々そこから追いつくという事は大変になるかなという話ではあるかと思います。
ですが、ポイントを押さえていけばそんなに量が多いという訳ではないので、という事は言えるのではないかなと思います。
そういった中でどのタイミングで受験するという事を決心するのか、決心するのであればどういった方向性で受験というのを行っていくのかという事を考えながらタイミングを見計らって頂ければいいかなと思っております。
低学年から受験に備えてやるべき事は?
これもよく言われる話ではあるかと思います。
一般的ではありますが、例えば小学校4年生から受験勉強を始めるという時に、もちろん4年生用、5年生用、6年生用のテキスト、6年生のテキストが当然圧倒的に一番多いですが、5年生、4年生用のテキストというものも世の中には沢山あったりします。
ただ、逆に3年生用、2年生用、1年生用のテキストはそんなに量が多くないんです。
何冊かその候補があって、その中からレベル別に応じて色んな問題を解いて、色んな学習をしていって欲しいという事になるという事になりますが、どちらかと言うとカリキュラムは先取りして勉強するというよりは、その段階で出来る事の深みをもうちょっと増やして欲しいというのが最終的な結果から考えられるべき所ではないかなと思います。
例えば、足し算、引き算、掛け算、低学年だから割り算も一応含めたあたりの基本的な計算というものがありますが、それが解けるという事とスピーディに解けるという事の違いが結構あるかと思います。
結局その受験というか、そのテストにあたるものは基本的には制限時間が設けられていて、例えば入試であれば50分という制限時間が設定されています。
計算テストだったら10分ぐらいの制限時間が設定されています。
この制限時間の中でどれだけ解けるのかという事をちゃんとやっていかなければいけないとなった時に、ゆっくり丁寧にやって答えを出すという事ももちろん大事ですが、より重視されるべきはそれがちゃんとスピーディに正解出来るかどうかという所もあるかなと思います。
なので、何か色んな内容の事をたくさん勉強して欲しいというよりは、そのスピード感というものが養えていくといいんじゃないかなと思います。
というのがまず一つ目の回答になるかと思います。
それからよく言われるのが、色んな経験を積んでいた方がいいんじゃなかろうかという事で、特質するものがあるとするならば、色んな文章を読めている事、そして、例えばいろんな図形に対する認識が出来ている事です。
立体図形なんかでよく言われる話ですが、立体図形は空間認知能力が弱いせいで立体図形の問題が全く解けない、歯が立たないというケースは結構多いんじゃないかなと思います。
最終的に受験になったタイミングでは空間認識能力云々、優位以前に解き方というものが存在するので、それに従っていれば答えが出るという問題が比較的多い訳ですが、でも能力があるに越した事はないかなと思います。
なので、そういった教材なりなんなりを使いながらそういった色んな能力を高めていくという事をやって頂ければいいんじゃないかなと思います。
ちょっと話がごちゃごちゃになったんですが、ひとまとめにしますと、要は、先取りをするかどうかでいうと、先取りをしない方がいいかなと思います、というような所になるのではないでしょうか。
通信教育でも大丈夫か?
色んな通信教育で中学受験のカリキュラムを勉強出来るというサービスは近年そこそこの数があるんじゃないかなと思います。
当塾でもオンライン指導という形で通信教育というかどうかはちょっとさておきという所ではありますが、そういった形で通塾されなくても勉強を進める事が出来るという所は多いかと思います。
大丈夫かという質問についてはもちろんケースバイケース様々あったりしますが、この教材というものをどうやってうまい事使うのかという事が結構大事になってくるかなと思います。
要は、なんとなく毎月毎月送られてくるものをなんとなく毎月毎月解いて、それで毎月毎月なんかテストらしきものを受けてなんか結果が出た出なかったみたいな事を毎月毎月繰り返す。
それだけでやっていくと多分なんとなくどっかで追い付かなくなってくるというか、気が付いたらちんぷんかんぷんの内容を勉強しているんだけどよく分からんなこの話、という事が増えてくるんじゃないかなと思います。
どこかで、どこかのタイミングまでにこの内容はちゃんと勉強しておかなければいけないという事をちゃんと決めておいてもらって、それを目標にしてちゃんと勉強していく。
要は、通塾される場合と通信教育の大きな違いというのは、どうしても他の生徒さん、いわゆる同級生たちがどれぐらい勉強しているかというのが見えづらいという所が一番大きな点かなと思います。
なので、そういった点、要は、自分自身と戦うという形になりますので、目標とかいわゆるここまでにこれをやるという事はちゃんとしっかり決めてやっていくのであれば特に問題なく勉強は進められるんじゃないかなと思います。
合格実績のよい塾に変えた方がいいですか?
これもよく聞かれる質問です。
先ほど模擬試験の話でも似たような話をしたのかも知れませんが、当然ながら同じ志望校に対してたくさん合格している塾の方がいいに決まっているというのは確かにそうです。
ですが、それだけが大事かというと別にそういう訳でもないです。
要は、今の話は基本的には同じような環境で勉強する事が出来るよ、というメリットについてはいいだろうという話になる訳ですが、その生徒さん生徒さんによって課題感は大分違う訳です。
例えば、どこかの単元が凄い苦手というケースの何とかなきゃいけないという生徒さんもいる一方で、全般的に例えば凄いミスが多いなとか、凄い計算を間違うな、とかいう生徒さんもやっぱりいらっしゃる訳です。
そういった中で、それに対する個別個別に対するフォローというのが出来ていくのかどうかというのは塾さんによってだいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。
なので、そこら辺を見極めた上で考えておいてもらった方がいいかなと思います。
結局はどういう感じで塾というか授業というか、というのを受けられるのかなという事が一番大事ではありますので、実績だけが全てではないかなという事はご認識頂けるといいとは思います。
※状況を整理するための判断材料です。
- 授業を聴いて帰ってきたはずだが、翌日に残らない
- 宿題と直しが回らず、積み残し化している
- 後手に回りすぎて、何から手を付けるべきか分からない